Hassamu history
発寒の歴史
━━開拓の頃
 西区は、左股川、琴似発寒川を境にした東側一帯の琴似町地域と西側一帯(発寒地区は 旧琴似町に含む)の旧手稲町地域からなっています。これらの地域には、和人の入地以前からアイヌ民族が生活を営み、独自の文化を築いていました。
西区は、左股川、琴似発寒川を境にした東側一帯の琴似町地域と西側一帯(発寒地区は 旧琴似町に含む)の旧手稲町地域からなっています。これらの地域には、和人の入地以前からアイヌ民族が生活を営み、独自の文化を築いていました。- 旧琴似町地域の中で、和人の居住が入地記録上早くから見受けられたのは発寒地区でした。安政四年に幕府旗本の武士20名とその従者が辺境の警備と開墾のために入地しましたが、一村を形成するには至りませんでした。
━━明治の頃
- 明治4年に開拓使が現在の南四条通以南に近在の移住者を集めて作った辛未しんび村から44戸が同年、八軒、二十四軒地区などに移住し開拓に従事しました。しかし、本格的な開拓は屯田兵によるもので、明治7年の屯田兵例則の制定が開拓の発展に大きな影響を与えました。
- 仙台亘理わたり藩(宮城県)・斗南となみ藩(青森県南部地方)・庄内藩(山形県)の士族たちが、明治9年に発寒地区(現在の稲荷線沿い)にそれぞれ入植し屯田兵村を形成しました。
- その後、周辺地域の開拓も進み、発寒・八軒地区は牧畜。山の手地区は畑作へと地域の特性を生かした農業が行われるようになり、屯田兵による開拓は制度が廃止される明治37年まで続きました。
━━明治の頃その二
 『在住』というのは、昔の中国の屯田制度にならって江戸幕府が考えたもので、北海道を外国から守りながら、開拓をすすめようという制度です。
『在住』というのは、昔の中国の屯田制度にならって江戸幕府が考えたもので、北海道を外国から守りながら、開拓をすすめようという制度です。- 安政元年頃、ロシアの人がなんどもシベリアから北海道に来たり、オランダの船が北海道の周りを探検したりしていました。
- そのために、幕府は北海道を守らなければならないと考えて、近藤重蔵・最上徳内・松浦武四郎らに、北海道を調べさせ、「在住」の場所を、釧路の白糠、苫小牧の勇払と石狩のアッサム(ハッサム)と決めました。
- 白糠と勇払には、1800年(寛政12)八王子同志(武士)百名が入地しました。しかし、当時の北海道の気候や生活に合わず四年で本州へ帰ってしまいました。発寒には、1857年(安政4)に、今の稲荷通りの両側に建てた家(官舎)5軒に住みました。
- 「在住」の人たちは、発寒に入地の前は、下級武士でした。その人たちは人夫として働かせるため、農民を一緒に連れてきて、農業をさせましたが、1866年(慶応2)で、この地に入地した人たちは本州へ帰ってしまいました。開拓された土地は、幕府の小手作場となり、新しく入地した人にあたえられました。
- この「在住」の役宅(官舎)や農業の仕方や生活の仕方が参考にされ、屯田制度のさきがけとなりました。そして、1874年(明治8)琴似に屯田兵198名が入地し、明治9年5月21日、私たちのまち発寒に屯田兵32戸が入りました。山岡精次郎らが1857年に「在住」として発寒に移住してから、20年が経っていました。
- (発寒小学校資料室の説明から)
━━昭和の頃
 昭和30年に琴似町が、42年には手稲町が、それぞれ札幌市と合併。その後の人口増加に伴い、農地は次第に住宅地と化し、街は大きく様変わりしました。
昭和30年に琴似町が、42年には手稲町が、それぞれ札幌市と合併。その後の人口増加に伴い、農地は次第に住宅地と化し、街は大きく様変わりしました。- 昭和51年には地下鉄東西線が開通し、これを契機により一層の人口流入が続き、昭和48年に西陵中学校、50年には発寒東小が開校、西陵橋、西陵公園が完成するなど、発寒の街づくりが進められました。
━━平成から現在
- 平成元年11月6日、西区を分区して手稲区と新しい西区が誕生。
- 平成6年には、はっさむ地区センター、発寒流雪溝が完成。同時にカラー舗装、おしゃれな水銀灯へ切り替えられ、並木も銀杏が植えられ、稲荷街道は『ぎんなん通り』という愛称で親しまれるようになりました。
- 平成11年2月25日、地下鉄東西線延長部(琴似~宮の沢間)が開通しました。
資料、写真協力:発寒小学校、発寒東小学校

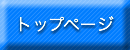

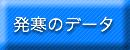
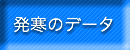


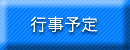





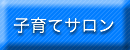
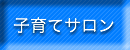

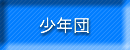
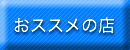
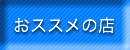






 前のページへ
前のページへ